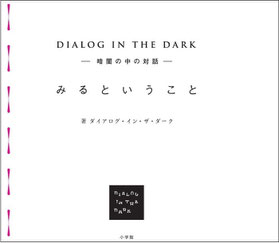
年末年始は本を読み漁りました。そのうちの1冊がこの本です。実はこの本が扱っている「ダイアログ・イン・ザ・ダーク(以下DID)」に関連する他の本も数冊読みましたが、まずはこの本から紹介していきたいと思います。DIDは1998年にドイツで始まり、ヨーロッパ各地に広まり、そして日本では1999年に始めて開催され、現在は東京・外苑前の会場に常設されて行われています。照度ゼロ(まったく光が入ってこない)暗闇に公園や広場などの日常空間をつくり、その中に8名の参加者がグループで入っていきます。そのグループを案内するのは、アテンドと呼ばれる視覚障害者の方です。目の前さえ全く見えない状況の中、まるで見えているように道案内をする視覚障害者の方にリードされながら、参加者は視覚以外の感覚をフル活用し、他の参加者たちとも協力しながら進んでいく対話型のワークショップです。DIDのアイデアが画期的なのは、視覚障害者が暗闇の中を誘導するエンターテイメントであるということです。暗闇に入ると、あっと言う間に目が見えるはずの私たちは無力になり、私たちの社会でありがちな健常者と視覚障害者という図式は逆転するのです。
私たちは彼ら彼女らの声を必要とし、入口で渡された白杖が目の代わりになることを知ります。普段の生活のなかでは身体がぶつかったり触れてしまうと不快に思っていたにもかかわらず、暗闇のなかでは周りに人がいるという安心感につながります。また、暗闇の中では人の見方も変わります。仲間になったその人が、何歳なのか、どんな仕事をしているのか、収入が多そうなのか少なそうなのか、美人なのかイケメンなのか、誰ひとり分かりませんし、知る必要もないのです。そこには人の内面しかありません。やがて障害がある人、ない人という垣根さえも暗闇の中に溶けていく。外見から解放されたことで私たちは不思議と自由になるのです。
この本を読もうと思ったきっかけは、視覚障害者のガイドヘルパー養成研修をいつかやりたいと思っているからです。私が他の介護スクールで働いていたときに、視覚ガイドの研修は何度も手掛けてきましたが、納得のできるものではありませんでした。決まり切ったカリキュラムの中で講義があり、演習はアイマスクをして街中を歩き、電車の乗り降りをする。それはそれで面白く、良い経験になるのですが、私としてはそれだけでは不十分と感じていました。なぜかというと、今にして思えば、私たち健常者が視覚障害者を介助してあげるという図式から抜け出せていなかったからです。
DIDについて知ったときに感じたことは、見ることができない視覚障害者の気持ちを理解して、介助するという考え方自体が愚かだったのだということです。視覚障害者は視覚を失ったゆえに、他の感覚が立ち上がり、私たちには感じられない豊かな世界を生きているのに対し、私たちは見えることによって、本来持っているはずの他の感覚を失い、目で見えるものや情報に振り回されて、縛られて生きているのかもしれません。私は今の日本の外面だけの社会に辟易しているところもあり、もっと私たちは人間的に豊かな関係を築けるのではないか、私たちの凝り固まった価値観など捨ててしまいたいとさえ思っています。そのためにもぜひ近いうちにDIDに参加し、彼ら彼女らの生きている世界を教えてもらうつもりです。


