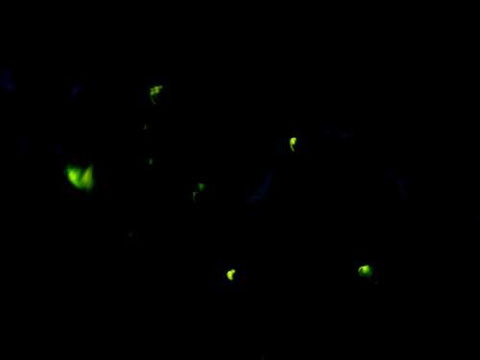
先日、鎌倉広町の森へ蛍の鑑賞に行ってきました。地域のコミュニティ活動の一環として開催された鑑賞会に、家族で参加しました。心配していた雨も直前に降り止み、まさにホタル日和。現地に集合して、まだ明るい夕方6時ごろから歩き始めると、次第にあたりが薄暗くなってゆきます。途中で桑の実を見つけ、小学生の息子が食べてみましたが、まだ未成熟な赤い実で少し酸っぱかったようです。森の奥地に到着する頃には、気が付くと闇が深くなっていました。
今年初めて観た蛍は、実に力強い光を放って飛ぶ源氏蛍(ゲンジボタル)でした。1匹飛びだすと、あちらこちらに2匹目、3匹目と、蛍たちは私たちの目の前に姿を現し始めます。手が届きそうで届かないところを飛ぶ蛍もいます。飛ぶというよりは、雪が舞い落ちるようなスピードでゆっくり下がったと思ったら、今度はスーッと空に向かって昇っていったりと、実に幻想的な光の景色でした。
引率してくれたボランティアの方のお話によると、蛍が光を発するのは求愛行動の一環だそうです。夜行性の蛍は、お互いに存在を暗い中でも知らしめるために発光する能力を獲得したそうです。なので、暗いからといって、私たち鑑賞者が明るいライトを照らしたりすると、蛍にとっては誰が蛍で誰がそうでないのか分からなくなってしまい、混乱してしまうこともあるそうです。できる限り、ライトを照らすのはやめてくださいと言われました。
また、源氏蛍と平家蛍の両方を観ることができました。ふつうはどちらかが多いときはどちらかが少なく、入れ替えのような形で現れるため、両方をきちんと観ることができる時期というのはほとんどないということですが、とてもタイミングが良かったそうです。源氏蛍は体が大きい分(15mm前後)光が明るく、光ってから消えるまでの間隔が短かったです。対して、平家蛍は体が小さい分(8mm前後)、光は弱く、光ってから消えるまでの間隔が比較的長かったです。同じ蛍でも種類が異なれば、光り方までこんなに違うのだと、初めて知りました。
蛍といえば、いつも思い出してしまうのが、小林秀雄の蛍のエピソードです。死んだ母が蛍になったと感じたという何ということのない話ですが、なぜか不思議と印象に残っています。せっかくなので、少し引用させてもらいますね。
終戦の翌年、母が死んだ。母の死は、非常に私の心にこたえた。それに比べると、戦争という大事件は、いわば私の肉体を右往左往させただけで、私の精神を少しも動かさなかったように思う。(中略)母が死んだ数日後のある日、妙な経験をした。
仏に上げるロウソクを切らしたのに気づき、買いに出かけた。私の家は、扇ガ谷の奥にあって、家の前の道に沿って小川が流れていた。もう夕暮れであった。門を出ると、行く手に蛍が一匹飛んでいるのを見た。この辺りには、毎年蛍をよく見かけるのだが、その年は初めて見る蛍だった。今まで見たこともないような大ぶりなもので、見事に光っていた。
おっかさんは、今は蛍になっている、と私はふとおもった。蛍の飛ぶ後を歩きながら、私は、もうその考えから逃れることができなかった。
お母さんが蛍になるわけがないと切り捨てるのは簡単ですが、小林秀雄にとってはそう感じられたのであり、またその小林秀雄の文章を読んで、私も共感し(同じように感じ)ました。小林秀雄のお母さんが蛍になるなど、科学的にはあり得ない話ですが、脳内現象としては実際には起こっているということです。人間が体験することは全て、脳の中の一千億のニューロン活動によって引き起こされる脳内現象である以上、目の前の光を蛍と見るか、おっかさんと見るか、どちらもあり得ることで、そうやって私たちは世界全体を引き受けて生きているのです。
尊厳死を扱った「海を飛ぶ夢」という映画の中で、四肢麻痺で28年間寝たきりの生活を強いられている主人公が言ったセリフ「僕はいつだって海へ行ける。想像の翼で。空を飛んでいく」の意味が、この歳になって、ようやく少しずつ分かってきた気がします。目の前にあるものが全てではない。同じことを見ても、人それぞれに違うものに見える。私たちは想像し、自由になれる。そう考えると、ちょっと気が楽になりますね。


