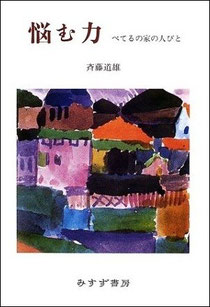
この本に出会ったのは、今から10年ほど前のことでした。介護の先生の机の上にずっと置いてあり、タイトルや表紙の絵からはどんな内容の本なのか想像すらつかなかったにもかかわらず、ずっと気になっていました。ある日、ふと書店の棚にその本を見つけ、ほぼ衝動買いのようにして手に入れました。読んでみると、北海道の浦河にある、精神障害を抱えた人々が共同して生活する場(べてるの家)を舞台としたレポでした。重い内容かと思われるかもしれませんが、実にユーモラスで、私もその人々の生活の中に入り込んでいる錯覚に陥ることもあるぐらい、丁寧な取材に基づいて描かれています。
精神障害について書かれた本の中で、これ以上のものはないのではないかと思うぐらい素晴らしいのです。この本の大切だと思われる部分は、ノートに写し取って、今でも残っていますので、それを紹介させてください。実際の言葉を読んでもらうほうが、著者がべてるの家で見てきたもの、感じてきたこと、気づかされた私たちの姿を理解しやすのではないでしょうか。以下、かなり長くなりますが、引用することで紹介に代えさせていただきます。
「その生き方、暮らし方からは、「そのままでいい」というメッセージがつねに発信されている。それは理屈を考えた結果ではなく、みんながともに暮らし、悩み、苦労しながら試行錯誤を重ねるなかで積み上げた結果だった。
それはもしかしたらいわゆる健常者の社会では実現できないことだったかもしれない。働けないものは寝ててもいいという、そんな不平等なシステムを一般社会は許容しないからだ。けれどべてるの人びとは知っている。精神障害者のなかには、働きたくても働けないものがいるということを。病気が出れば働けなくなるものがいるということを。そのことを認め、安心してサボっていてもいいと保証したとき、彼らは本当の意味で自由になった。その自由と安心感が最後には商売につながっていく。だれも切り捨てないということと利益をあげるということは、けっして相反するテーマではなかったのである。
そのような彼らとともにいるうちに、訪問者はそこにあぶりだされてくるのがけっして精神障害者の真実の姿などではなく、彼らの前にいる自分自身なのだということに気づくのである。飾らず、作らず、そのまま生きているべてるの人々の前にいるとき、仮面をかぶり、体面をとりつくろうことに懸命で、いつも周りの評価を気にして奮闘し、気が休まることのない「こっけい」な自分というものが見えてくる。
べてるの家が、ただの障害者の共同住居ではないと思わせるのは、この瞬間なのだ。人は精神障害者との出会いを目指してここにやってくる。そして、なるほどこれが「こころ病む人々」なのかと多少は理解したつもりになっている。けれど彼らと対峙するうちに、彼らの話に耳を傾けるほどに、自らの中にしだいに湧き上がる違和感、内なる声の問いかけを抑えることができない。目の前にいる人々の、こころ病むはずの彼らのなかにある底知れぬ安心感に対して、自分自身が抱え込んでいるのは、なんとちっぽけな不安の均衡だろうか。そのちがいはいったいなんなのだろうと、そのように考え出すその瞬間。訪問者はそこで鏡に映し出されたように、自分自身の姿と人生を見てしまう。自分は病気の人に会いにきたのではなかったか。だのに病者はいったいだれなのか」


